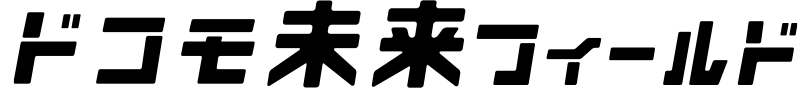2025年3月29日(土)

研究って奥深い!「人類学」のセカイに
どっぷり
浸かる特別体験に密着

2025年3月29日(土)、「国立科学博物館」に全面ご協力いただき、プレミアムな体験イベントを開催しました。抽選で当選した子どもたちと保護者20組を招待して、ここでしかできないさまざまな体験をとおして「人類学のセカイ」にふれてもらいました。
当日は、茨城県つくば市にある「国立科学博物館 筑波研究施設」でワークショップや収蔵庫ツアーを楽しみました!

人類学って?貴重な標本で「研究」の
セカイにふれる!
桜の開花が目前の中、当日は桜雨となり一気に気温が下がりました。つくばの「国立科学博物館 筑波研究施設」に訪れた参加者は、きんと冷えた空気の中、初めて入る施設に緊張と期待に胸を膨らませていました。

会場に着くと、そこにはいきなり本物の頭骨が!子どもたちは興味津々に近づいて、釘付けになっていました。
そこに国立科学博物館で働く森田 航研究員が登場しました!
主に研究されている「人類学」をご紹介いただき、人類学とはなんなのか、今研究でどんなことがわかっているのか、わかりやすくお話しいただきました

「この骨が人間の祖先って言われるのはなぜだと思う?」「人間の頭骨はどんなところが他の動物とちがうと思う?」と、森田さんから質問されると、子どもたちは、しっかりと声を上げて答えていました。これから始まる人類学という未知の世界の体験ですが、早くも楽しそうという予感がします!
森田さんから人類学を学んだ後は、本物の人骨標本を使ったワークショップがスタート!国立科学博物館のスタッフにサポートいただきながら、班にわかれてそれぞれ渡された骨を、人間の形に並べるワークショップです。

本物の骨に、びっくりしたり、怖がってしまう子がいるのではないかと心配していましたが、子どもたちは笑顔でワクワクしている様子。素手で抵抗なくふれて、まるでパズルでもやっているかのように、楽しそう。
まずは、大きめの骨から手に取ります。
この骨は、足の下半分にある太い骨でした。実は足のすねには骨が2本あることを並べていくことで初めて知りました!他にも観察していくと、左右で形が違ったり、つなぎ目で隣り合わせの骨が何か、少しずつ見方がわかっていったようでした。
ただ、いきなり人骨だけを見ても、どれがどこの骨か、全部はわかりません。
そんな時、困ったみんなの目の前に現れたのは全身揃ったレプリカ!

骨を持って近づいて、「この骨はどこの骨と同じだろう?」と初対面の子どもたち同士、力を合わせて探しました。
背骨や肋骨など見分けがつきにくいパーツにくると、みんな苦戦。スタッフにヒントをもらったり、レプリカに何度も近づいて観察してみる子どもたち。
実は首に近づくと肋骨の曲がる角度が大きくなることや、大きさが違うことに気づいていきました。

だんだん完成に近づいていきながら、その発見の嵐に、夢中になっていく子どもたち。集中した、生き生きとした表情が見られました。
自分の目で観察することにより、自分自身で法則性を見つけたり、新しい学びを得たり。「研究」のセカイにふれました。
やっとの思いで骨を並べたら、今度は人間と似た動物たち、チンパンジー・ボノボ・オランウータン・ゴリラの4種の骨が登場!
横に並べることで、ゴリラはやっぱり大きいんだなとか、骨の違いから人間との歩き方や生活の仕方の違いを体感しました。

大量の標本でわくわく!収蔵庫ツアー
ワークショップで骨の仕組みをいっぱい学んだ後は、普段入ることのできない貴重な収蔵庫のツアー!
まずは森田さんの案内で人類学の資料が詰まった人類標本室に。
部屋の壁一面に並ぶ大量の骨は圧巻!なんとここつくばの人類研究部(イベント当時)には、他の保管室も合わせると約20,000体の人骨があるとか!その一部を今回見せていただくことができました。

縄文から江戸までの人骨があり、ネアンデルタール人の埋葬のレプリカなどを見て、人類の進化や過去の文化をどのように研究しているのか、深く知ることができました。
子どもたちも積極的に森田さんに質問。丁寧に教えていただいて知識を深めていきました。
続いて、川田 伸一郎研究主幹のご案内のもと、陸生哺乳類標本室を見学しました。そこには、約1740点のさまざまな動物たちの剥製がずらり!

大型から小動物に至るまで、中には絶滅危惧種の剥製など、一般公開されていないスポットに子どもたちはワクワクしながらきょろきょろ観察。川田さんから剥製を集めた経緯や想いなど、たくさんお話しを聞くことができ、動物の研究についても知ることができました。
どんな人だったんだろう?
見て、考えて、みんなの前で発表!
イベントの最後は、体験したワークショップの集大成、「発表会」です。
改めて、今まで並べてきた班ごとの人骨がどんな人物だったのか?考察して発表します!
研究は自分の考えを練って、発表することが大事。

改めてスタッフや森田さんの力を借りながら、班ごとに考えを固めます。最後の大詰めです!
いざ、考えをまとめたら、班ごとに発表していきます。時々、人前の発表に緊張して譲り合ってしまう様子もありながら、勇気を出して班の考えを述べる子どもたち。

「顎の形から、男性だと思います」「歯が黒くなっていたので、おはぐろを塗っていた、女性だったと思いました」「親知らずが埋まっていたので10代の人だったと思います」など研究者や保護者も驚く鋭い観察力を披露しました。
緊張しながらも、自分の言葉で考えをしっかり述べて、みんなから拍手をもらいました!
いっぱい観察したレプリカと記念撮影も。
きっとこの経験は忘れられないものになったのではないでしょうか。

参加者の方には特別展ペアチケットをプレゼント!
今日学んだ知識をもとに、ぜひ新たな視点で楽しんでいただけたら幸いです♪
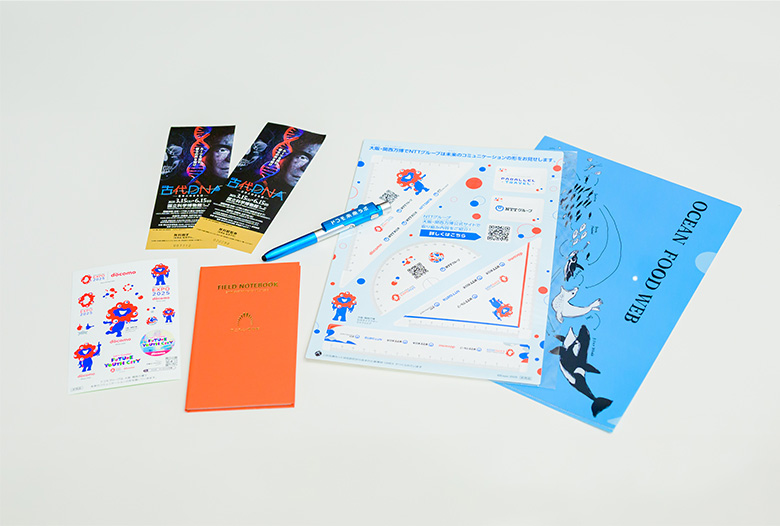
<森田研究員インタビュー>

Q:なぜ自然人類学を研究しようと思ったのでしょうか?きっかけを教えてください
小さい頃から考古学とか古生物学とか、古いものを研究することにすごい興味を持っていました。中学の頃からマヤ文明やアンデス文明など、中米とか南米の考古学をやりたいと思っていました。
そんな中、初めて中米にある国で発掘調査に行ったときに、たまたま初めて掘った遺跡が埋葬後の遺跡で、人骨がたくさん出てきたんですね。そのときに人骨の方に興味を持ったのですが、考古学ではあまり人骨は扱わないことを知って、「僕がやりたいことは考古学じゃなくて人類学なのかな」と思うようになりました。
Q:人類学や歯の進化の研究をしていて、一番おもしろいと思うことは何ですか?
僕は大きく分けて二つのプロジェクトをやっていて、一つは人類の進化の研究で、発掘調査に行くことがあります。そのときに何か重要な化石や遺物を実際に自分の手で掘りあげた時がやっぱり一番、すごい興奮するところかなと思っています。
もう一つは歯の進化の研究をしていて、歯の形が変わる過程で何が起きているのかっていうことを知りたくてスンクスっていう生き物を使って研究しています。そのなかで意外な発見に行き着くまでに、やっぱりすごい時間がかかるんですけど、過去の先生方が研究してきたことと関連が見えてきたりすると、「やっぱり自分がやってることがいい方向に行ってるんだなあ」と思えてすごい楽しい気持ちになりますね。
Q:研究者になるには文系や理系など、いつ頃から進路を決めたら良いでしょうか?
進路について僕は、結構年をとってからでもいろんな方法があるかなと思っています。
実際に、日本の教育制度で言うと文系と理系っていうのはすごい分かれてしまってると思うんですけど、例えば僕のケースで言ったら僕は文系で大学に入ってます。考古学って文学部にあるので。ただその後、自然人類学に行ってるので理系に変わってるんですね。
なので本当に自分がやりたいのが何なのかっていうことを考えて、そこに文系だから、理系だからって自分の中でハードルは作らないで、自分が知りたいことがあったら「この知りたいことをやりたいんだ」っていうふうに思ってもらえたらなと僕は思います。
Q:今後したいことや、夢はありますか?
今、発掘調査をやってるんですけれど、やっぱり教科書を書き換えるような新しい発見をしてみたいなと思っています。実際にすごい重要な発見を、日本の人類学者の先生たちがこれまで何回もやってきているので。
そこにつながるような研究を、もう本当に日々の積み重ねって、ちっちゃいものでしかないんですけど、それがちゃんと積み上がっていくように努力していきたいなと思っています。
Q:研究者になっていなかったらどんな職業についていたと思いますか?
研究にすごい興味はあったんですが、サッカーもずっと小さい頃からやっています。海外に発掘調査なんかにも行ったりすると、若い人たちで全然有名じゃないリーグだけれど、海外のリーグで頑張ってるっていう日本人の人と結構会ったりするんですね。
そういう人達を見てると、自分もサッカーをやって、もうサッカー無理だと思ってから研究に戻ってきてもよかったな、とちらっと思ったことはあります。(笑)
Q:森田さんは博物館所属ですが、研究者という職業はどのような就職先があるのでしょうか?
研究職は狭き門なので、僕も大学院に進むときに当時の先生に本当に進むかよく考えろとアドバイスをもらいました。研究職というと、やっぱり大学に行くか博物館に行くかが、中心になるかなとは思います。とはいえ、製薬会社とか企業に行って研究していらっしゃる方もたくさんいます。さらに小学校とか中学校とかの教員で生物が好きで生物の研究をやってらっしゃる方もたくさんいるっていうのは僕も科学博物館に来て初めて知りました。分野によるんですけどあとはお医者さんっていう道もあるかなとは思います。
なのでそういう意味では、好きなものがあったらそれをずっと追いつづけるっていうことはいろんな道があるのかなと思ってはいます。
Q: 研究者になりたい、体験で人類学に興味を持った子どもたちに一言お願いします。
今日やったことで、生物学とか進化とか人類学とかに興味を持ってもらえたら非常に嬉しいですし、僕も非常に楽しませていただきました。それぞれ面白いポイントって違ったと思いますので、自分が面白いなと思うことがあったら、別に人類学を専攻しなかったとしても、それを突き詰めていくような、これがやりたいんだって思えるものをぜひ見つけて、それに向かって努力してほしいなと思っています。
博物館にもぜひ来ていただきたいです。
写真提供:国立科学博物館